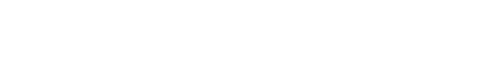2023-10-12
インテリア会社のルートセールス木村さんの話:リストラという現実を知る
僕が初めて会社のリストラの現実を知ったのは、新卒で入社したF社に入った後、約9ヶ月目のことだった。ある意味、リストラの現実やこの社会の厳しさを入社して1年も経たないうちに知ることができて、本当に幸運だったと思う。当時、約30年前はバブル崩壊直後で、リストラという言葉も使われ始めたばかりだった。
もしリストラという現実を早く理解していなかったら、この資本主義社会、すなわち能力主義の現実を理解するのにもっと時間がかかったかもしれない。この時点で「利益を出さない者は切られる」というリストラの真実を知ったことで、以降の転職活動や新たな会社での経験においても、ある程度の覚悟を持つことができ、危機感を持つことができた。
今回は、私の会社の上司だった木村さんのリストラの話をしていきたい。この話は今でも鮮明に覚えている。しかしながら、リストラという現象への自分なりの解釈は、年を取るにつれて少しずつ変わってきている。最初は会社のやり方を非難していたし、会社は結局、社員を道具としてしか考えていないと感じていた。そのため、会社に見捨てられないように、しっかりとした人間にならなければと強く思っていた。今でもそう思っているし、そうあるべきだと考えている。会社は利益を追求する存在である以上、利益を出さない人間は必要ないというのがその原則だ。
僕は部長からよく叱られていたが、僕よりもっと部長から叱られている人が一人いた。それは木村さんだった。
木村さんは当時53歳くらい。会社の在籍も長く、30年近くものベテラン社員だった。しかし、何かの理由で、木村さんが担当している取引先の売り上げが低迷していた。メインの取引先は「キンカ堂」というアパレル・インテリアのチェーンだったが、実際、このキンカ堂は2009年に倒産している。
木村さんと部長は、地下のショールームでしばしば二人きりで話していた。僕はショールームの掃除をしているふりをしながら、二人の会話を盗み聞きしていた。ほとんどの会話は、部長が木村さんに売り上げについて詰め寄るものだった。そして、そのような面談が2日おきくらいに行われていた。最終的に木村さんは部長から辞めるように迫られ、事実上の解雇となった。
ある日の朝礼で、部長が木村さんの退職について発表し、木村さんに挨拶を求めた。
木村さんは50代半ばで、再就職先も見つからない中での退職だったので、彼自身辞めたくなかったと思われる。涙を抑えながら、堂々とした挨拶をしたのを覚えている。確かに、彼は酒癖が悪く、時には酒に酔って暴れることもあった。しかし、その一方で、面倒見がよく、冗談も言ってくれる人だった。木村さんの退職に際して、引き継ぎの同行があったが、彼はバイヤーに私を紹介し、最後まで粘り強く営業活動をしていたことが印象的だ。
その出来事を通じて、僕はリストラの現実を痛感した。つまり、会社にとって価値がないと見なされると、容赦なく排除されるのだ。そして、自分自身もいつリストラの対象になるかわからないという不安を感じるようになった。
後から知った木村さんの過去
木村さんが退職後、物流センターの仕事帰りに上司の山口さんと夕飯を共にした際、木村さんの話題になった。その部のメンバーは、ほぼ全員が木村さんの退職を不憫に思っていたようだ。彼らはリストラを仕方ないと感じながらも、「他に方法はなかったのか?」と疑問を持っていたという。山口さんも木村さんの解雇は厳しすぎたと感じていた。
木村さんは、もともと大学卒業後に入社し、若い頃は社内でのエリートとされていた。実際、高卒の部長よりも昇進が早かったとのこと。彼は新しく設立された絨毯部門を任され、当時はエネルギッシュで情熱的に仕事に取り組んでいた。しかし、その部門のビジネスが順調に進まず、結果として部門は廃止された。
30代後半か40代頃、木村さんは自ら会社を辞めたいと提案したことがあった。だが、その時の彼はまだ実力を持っていたため、会社は彼の退職を許可しなかった。私の推測に過ぎないが、おそらく彼が競合他社に転職することを恐れていたのだろう。それにより、大きな売上を失うリスクが考えられた。このような背景から、彼の退職を許可しなかったのだと思われる。
結局、木村さんはそのタイミングで退職することができず、しぶしぶ会社に留まることとなった。その後、彼は酒に逃げるようになり、仕事への情熱も失ってしまった。次第に業界や仕事に対する興味を失い、日常業務をただこなすだけの存在となったという。
山口さんは言った。「会社のやり方が残酷なのは、本人が辞めたいときに辞めさせず、本人が辞めたくないときに辞めさせることだ。」会社の利益優先の態度がそこに表れていた。昔の木村さんを知る者にとって、彼がこれまでに会社のために築き上げてきた実績は計り知れないものがあった。会社として見れば、彼のこれまでの功績と現在の状態を天秤にかければ、まだ彼には価値があったはずだ。だが、その事実を無視する会社の冷徹さを感じずにはいられなかった。
会社との冷徹な関係を知る
僕もこの時、初めて会社というものが残酷で冷たい存在であることを痛感した。この社会で生き残るためには、常に自分の生産性を上げ、利益をもたらす人間にならなければならない。いくら非情に感じるかもしれないが、会社とは結局のところお金だけの関係とも言える。そう考えると、使い捨てのように扱われる会社のために自分の命を削る必要は全くない。それをすることはバカらしいと思うようになった。
この考えが僕の心に深く根付いたのか、その後、僕は何度か営業の職を転職した。その際、遠慮なく前職の顧客を新しい会社へと引き連れることもあった。それは単なるお金だけの関係だからだ。前職の会社への義理堅さや忠誠心など、そういったものを持つ必要は感じなかった。次のステップで生き残るために、転職時に顧客を持ち去る行為は、自分にとっては正当な行為だと感じていた。
木村さんの事件: 新たな視点
30年のビジネス人生を経て、今、私はおそらく当時の木村さんと同じ年齢くらいになったと思う。その間に、私の考え方はかなり変わった。より客観的に、より全体を見渡せるような視点が身についたと感じる。当時、私は部長を冷酷な人と見ていたが、今思えば、部長自身が一番辛かったのではないかと思う。部長として、当時の赤字部門の存続を考え、リストラを行う側としての重圧があったのだろう。部長と木村さんは同期だったと聞いている。同期を解雇することは、心情的にも非常に困難だったであろう。
部長の上には2代目社長がおり、彼は有名な大学を卒業した後、他社から移籍してきたらしい。部長と社長の間には明らかな距離があった。経営層と現場との間には大きなギャップが存在した。暗黙のうちに「赤字部門ならば人件費を削減せよ」という経営陣の指示があったのではないかと推察される。木村さんの給与はかなり高かったと聞く。そのため、彼のリストラは経済的な選択としてやむを得なかったのだろう。インテリア部門には約12名の社員が在籍していた。彼らの生計を考慮すれば、木村さんの解雇は避けられない選択だったのかもしれない。
今となっては、部長自身が一番心を痛めていたのではないかと思う。
そして、木村さんにとっても、リストラされることは必ずしも悪いことではなかったのかもしれない。その後、私も複数回の転職を経験した。ある会社は自分に合わず、またある会社は最適だった。リストラや退職を経て、次の場所や仕事に移ることが、結果的には良い選択となることもある。リストラは、新しい場所へ行くようにという「天のメッセージ」や「卒業証書」であると捉えることができる。
結局、必要以上にしがみつくことなく、流れに身を任せることが大切だと思うようになった。振り返れば、木村さんにとってもリストラは逆に良い転機だったのかもしれない。もしかしたら、それは彼にとっての「卒業」だったのかもしれない。